こうしたブログに書く内容は、どれだけ私的なことを含めていいのだろうか。私は中学校3年から、2浪して大学に進学した20歳の頃まで、日記を毎日欠かさず書いていた。大学入学直後から児童養護施設で住み込み児童指導員を始めた。24時間勤務でメチャ忙しかった。欠かさず書いていた日記も、気づいたら2,3日空白が出始め、いつの間にか完全に書かなくなった。以来、日記はつけていない。
このブログは日記ではない。しかし、元来、書くことが好きなのだろうか、気づいたら、移動中の機内や路上脇のベンチなどで、ほとんどを書いている。日記は、どこかで、誰かに見られても仕方がないと感じて書くものだろうか。少なくとも、死後誰かの目に留まってもいいように自分をさらけ出しているのだと思う。ブログも限りなく日記だと考えようか。我が精神遍歴の原点と感じた「生月島」の旅をここに書きたい。
どうしても来たかった場所であった。私には行きたい場所がいくつかある。随分、あちこち巡ったので、これから先行ってみたい場所はあまりないのだが、あげてみると、やたら島が多い。利尻島、三宅島、宮古島、五島列島福江島。島でないところと言えば、下北半島と潮岬くらいだ。ほとんど全国を回り歩いた。そうした中で最も行きたかった生月島である。(今、このブログを見直し校正している場所が、新潟県村上市から一日2便しか連絡船が出ていない「粟島」行きの船を待っている待合室にいる。人口340人、周囲23キロの島。海には雪が舞っている。その島の高齢者介護をどうするか相談を受けたのだ。)
さて、話は生月島のことだ。「生月大橋」ができる前は連絡船でなければいけなかった島。今は大きな橋が架かっている。だから、講演会の合間に、僕はここに来られた。
佐世保駅から休まずレンタカーでここまで来たので、橋のたもとの道の駅に立ち寄る。旅に出る度に、景品買いをする習慣がいつのころから身についている。年末の望年会の景品買いである。望年会では、藤原の景品を贈ることが恒例となった。1年をかけて、全国あちこち訪れる度に買いあさる。日持ちがするもので、もらってうれしいもの、300円から1000円以内のもの、これが目安。店員の二人の女性は、「もう、望年会の景品ですか?」と驚きながら、「これどうですか」と目の前にいろいろ差し出す。「いいね、いいね」と調子に乗った。
目指す生月島の宿には5時半についた。ついてすぐ6時から、実は夢のみずうみの仕事が待っているのだ。完全休暇というのは今の私にはありえない。まずは、仕事だ。
防府デイ、山口デイ、浦安デイ、さらにはこの日、別場所にいる二人、私と、もう一人、宮本志郎首都圏統合施設長との5か所を結んで、V-CUBEというテレビ会議をするのだ。「介護保険制度の改定に伴っての対策協議」3回目。
「7時過ぎには夕食にしてください」と宿の女将から言われていた。30分遅らせてくださいと頼んでいたにもかかわらず、会議は終わらない。
女将が何度も「食事です、準備ができております」と声をかけてくださる。申し訳ないが、会議の方が重要だ・・・!!! 夜は更けてどっと疲れが来た。
明けて3月3日、午後1時半から平戸で講演会をこなし、夕刻福岡まで戻り、常宿の博多西鉄イン泊。翌早朝、羽田に戻り、新横浜で講演するまでの「生月島休暇」である。
生月島は、14歳の時に、生月町に手紙を出した話から書こう。「あの橋のたもとで」というメロドラマがあった。戦後ラジオ番組で有名な「君の名は」の作家、菊田一夫が書いた脚本である。そこに生月島が出てくるのだ。テレビドラマは見ていないが、30代の島倉千代子が出演したそのドラマ。広告が新聞に載り、マドンナお千代さんに心がときめいた。本屋で小説を見つけて読んだ。そこに、主人公の彼女が、生月島に行く設定になっていた。「生きる」「月」「島」という言葉から醸し出すロマンチックな響きと、大好きな島倉千代子と悲恋話が少年の心を揺さぶったのではないかと思う。小説を書こうとしたこと自体理解できないが、どうしても尋ねてみたいと思い込んだことも今となってはよくわからない。しかし、やっと念願がかなった。
14歳の子供が、新聞に出ていた生月町役場の住所を頼りに、『小説を書くので、生月島に関する資料を送っていただけないか』と手紙を出したのである。ほどなく、町役場のどなたかから、結構な量の小包が広島の下宿先に届いた。いっぱい資料が包まれていた。今は跡形もない。その資料を片手に、いろいろイメージを膨らませたものだ。脚本も少し書いた気がするが手元にないし思い出せない。いい加減な性格そのもののエピソードだと我ながら驚くが懐かしい。50年に近い歳月が流れたことになる。
生月の最初に、「大バエ灯台」という場所を尋ねた。島の突端、高台に建つ。強風だ。以前、襟裳岬に立った時、やはり強風に吹かれた。その時よりはまだ緩い。襟裳岬では立っておられず、地面に手をついた記憶がする。しかし今日も結構な風だが立っておられる。
殉教の島、生月島に来て、熱心なカトリックの信者であった自分が突然変貌し始めている。それになんとなく気づきだしている。おそらく20代はじめだったろうか、ある時期から、「キリスト教は捨てた」「私は転びキリシタンだ」と吹聴していた自分がいた。いま、ここ大バエ灯台という島のはずれの寒風吹きすさぶ場所に立って、そのことを悔い始めている。なぜだか、悔いている。不思議な感情が湧き出てきている。キリスト教信仰ではない。宗教心とも違う。自分自身の内面から浮き出てくる感覚。過去の自分が今ここにいるという感覚であろうか。「捨てたのではない、離れたのだ。いつでも近づけるんだ」という思いがする。なぜだろうか。この場所、この生月の殉教者の聖地。
灯台の上に登って、360度東シナ海を眺める。灯台がかすかに揺れているような感覚がして、あわてて手すりを握りしめた。そんなはずはない。こんな灯台が揺れるかい? 「強風に気を付けてください」という看板の文字が恐怖心をあおったのか。本当に揺れている気がした。そんなはずはあるまい。しかし、高い灯台は、今、かすかに揺れて立っているのではないか、高い塔はそういう構造で強風に耐えているのではないか、などと勝手に想像しだすと、景色を眺める余裕などなくなり、怖くて下に降りた。
(パソコンを取り出し、レンタカー車内でここまで一気に書いた。)
「黒瀬の辻殉教碑」の前の祭壇にパソコンを置いて再び書きだす。ここが、生月のキリスト教徒の聖地である、(ここまで書いていたら、タクシーに乗って他の観光客が見えたので、すぐ下に続く公園の石のベンチに場所移動)
この聖地で、イエズス会神父が殉教している。「妻と子供と共に殉教」と碑文にある。
「え? イエズス会の神父は結婚してはいけないのではないか?」
かつて、高校1年生の時、広島学院の教師で神父でもあるアメリカ人のスミス先生から
「イエズス会の神父になれば、君の福祉の夢は実現できるよ。君は熱心な信者だから、どうイエズス会に入らないかい。考えてみないか?」と誘われた。
独身で生涯過ごす覚悟は16歳の少年にあったのだが、教義についていく自信がなかった。
だから、神父にはならず、イエズス会にも入らなかった。
生月島の大バエ灯台はすさまじい風だった。今、この黒瀬の辻殉教碑の前の祭壇は、風は収まって陽だまりに身をさらしている。
ここで殉教された神父は、妻帯されたようだ。そして子供も生まれた。少し驚いた。カトリックの神父の妻帯は許されないはずだ。プロテスタントの神父は許されている。この地で神父さんは、妻子ともども殉教された。そして、ここが生月島、隠れキリシタンの聖地となった。
涙が涌いてきた。
「なぜ、お前は泣くんだよ」と、叫んでみた。周りに誰もいないと思ったから、私は自分に声をかけた。
「わからない」
人を思う精神、弱い人(もの)をいとおしく感じる意識、強い権力を嫌う意識。お前は偽善者ではないか、そう、語りかけた時期も、若い頃随分とあったことを思い出す。結婚する前の20代前半ごろだったか。お前の福祉は偽善だと、高校時代に誰かと語り合っていたことも思い出した。養護施設時代は、もう、偽善もへったくれもない、ただ子どもが好きで、かわいそうな子供と思ったことなど一切なく、子どもたちと生活することをよしとした。大学に入って誘われたボランティアサークルの活動の延長で施設に住み込んだのだし、ただ性に合って、そのまま活動先の児童養護施設に住み込んで、福祉の道に入り込んでいたのだ。そのまま63歳まで、福祉の現場にいる。
「強くなくていい 弱くない生き方をすればいい」という拙著を書いた。その時、弱いものに自分が触れていく要因、幼いころから福祉を志した要因について書こうとした。その時には、この「殉教者」「迫害した者」ということを全く思い出さなかった。それほど、我が精神遍歴に影響していなかった要因かもしれない。しかし、生月島に来て、自分は全く忘れていた自分を思い出している。
ガスペル神父の記念碑があるが石が積み重ねられただけのものだが、そこに花を生ける筒が両サイドにおかれ、新鮮な花が活けて有った。石組みの後ろは、松の根元がむき出しになっている。お墓の前で十字を切った。自然とそうしたくなった。私の身体の中に秘められていたのか。何の不自然さもない。ただの石ころには見えなかった。見知らぬ神父の意思に十字を切ったのか。わからない、ただそうしていた。それが、私をして、我がキリスト教観、宗教観を考えざるを得なくさせていたと思う。
「迫害」「殉教」という事実に触れることによって、「弱いもの」「弱さ」と「真の強さ」というものに気付かされたのかもしれない。いや、それ以上に、実に何十年ぶりかで、神父さんの墓(というよりただの石のかたまりが置いてあるだけのモニュメント)を前にして、十字を切った自分。その自分のとった行為に自分で驚いている。迫害した人間のことを考えようとした自分。これまでは、殉教した人のことを主に考えていたような気がする。今日は迫害した人間のことも考えている。
キリスト教を捨てたのではなく離れているのではないかと思った自分。それもはっきりしないまま、生月島に浸っている自分がいる。
「殉教」という人間が人間に施した所業、権力が、人間の自由と精神を踏みにじった恐ろしさ。そういうものが我が精神の底にこびりついているのではないか。生月島はそれを私に教えている。
今、この生月の殉教の聖地に座っていて、自分の福祉の原点が、(もしかしたら、いや、確かに)“殉教”ということにあるのだと意識し始めている。島根県津和野町の乙女峠で迫害された少年たちや、殉教者の巡礼に参加した時のことを、如実に想起できる自分。今日、自分が無意識に切った十字架。自分の意識に潜在的に埋め込まれた、この“迫害と殉教”の人間業とそこに関わった人間の皆々。そして、この私。
ここに今立って、こうして風に吹かれ、そろそろ寒さを感じだした中、このワープロを打ちながらいろいろ書いて、感じている自分が生々しい。そのことを嬉しく思う。
どうしても、どう見ても、私はキリスト教の影響を受けている。それを生月、この地は知らしめてくれた。
また涙が出る。なぜ泣くのだろう。何に泣いているのだろう。無性に落ち着くこの場。私はキリスト教の教義を信仰していない。それは明白だ。しかし、キリスト教的環境の中で自分は落ち着いているし、落ち着く自分になることがわかる。それは生育歴から来るのか。
弱いものを迫害した権力、命を奪われても守ろうとしたもの、そういう強さと弱さというものの中に、自分は何かを感じ、血肉にしたのだろう。涙が出る。なぜ泣くのだろう。何に泣いているのだろう。無性に落ち着くこの場。
涙がどんどん涌いてきた。
「なぜ、お前は泣くんだよ」と、声を出して叫んでみた。周りに誰もいないと思ったから、私は自分に声をかけた。
「わからないよー」
信仰とはなんだろう。思春期から随分と自分自身が考え悩んだテーマであった。
「私はキリスト教を離れたのであって捨てたのではない」
そう自分で自分に言い聞かせている。なぜ、さっき、瞬間そう思ったのか。
「捨てたのではなかったのだ」「離れたのだ」「今は離れている状態だ」、自然とそういう思いが涌いてきたのだろうか。また、自分に問い返す。この地で、キリスト教徒の迫害、殉教、禁教令が出た江戸時代からの史実の記載に心が痛くなる。祭壇の前に自然に、ひざまずく。マリア像や、十字架を見ながら、思いを巡らす。
私は、十字をきっていた。キリスト教信徒は、教会に入るとき出る時、必ず十字を切る。右手の指で、額、胸、左肩脇、右肩脇に手を移動して十字を切る。小1の時から何十年もやってきていた習慣。やめてからの方が長くなってしまったその習慣。それが、ここにいて、祭壇ひざまずいたら、ふと自然に右手が動いたのだ。なぜだ。
中学3年の時、「血と雨」というシナリオを書き、広島学院の教会クリスマス会で、同級生や後輩を役者にして、私が演出し上演した芝居だ。毎年、私が脚本を書き、演出もして、クリスマスには芝居を上演した。覚えているだけでも4作になる。この「血と雨」は、長崎で殉教した26聖人の実話。とりわけ少年が迫害されて亡くなっている事実を知って書いた脚本である。この脚本自体は私の手元になかったが、ある日突然、「NHKのプロフェッショナル仕事の流儀」に出演した私を見た後輩が思い出して、懐かしくなり、持っていた台本をコピーして送ってくれたのである。
私の、殉教に対する思いはただ1点。
「どうして、それだけ信ずることが、あなた方はおできになるのですか」である。
命を賭してまで、どうして信ずることができるのか。相当な迫害を受ける。しかし、信仰を捨てない。むしろ、かたくなまでに信じることができる。
この黒瀬の辻殉教碑の前の祭壇から、島の湾の中央にある「中の島」という島がここから見える。殉教の島。何人もの信者さんが送り込まれ、迫害され殉教されたと碑文にある。小さな島だ。天国につながっていると信じて命を落としたと書いてある。相当数であろう。なぜ、そこで、死を持って天国に行けると信仰できるのだ。信ずる者は幸せだと、言い捨てるにはあまりにむごい、子どもへの迫害や人間に対する迫害の数々。時の権力には許される愚行なのか。かつて、神国日本が戦争をし、それに反対するものは罰せられる中、強いものに巻かれていく人間と、それにしっかり、はっきり反対できる人間とがいた。食べ物なし、殴られ、けられ、鞭打たれ、棒でたたかれ、海水を浴びせられ、「宗旨をかえろ、捨てろ」と迫害されたのである。
ふと、迫害した人間はどういう人間だったのだろうと思った。迫害をした側の人間のことを考えたことは、ほとんどといっていいほど過去においてはなかった気がする。以前は迫害を受けた人ばかりのことしか思はなかった。しかし、今、迫害した人間のことも思っている。
「血と雨」の迫害した直接の責任者、張本人、長崎奉行は、単なる悪人として、それなりに書いたつもりである。今、あの島で、何人ものキリスト教信者を迫害した人間のことを思う。外人の神父を迫害することは、外人嫌いという感覚も加わったかもしれないが人間業ではない。しかし、小さな子供の命を奪ってしまう心境は、全く持って理解できない。どういう人間の神経・感覚をしていたのだろうか。自分にも同じような年恰好の子どももいたろうに。妻子もいるだろうに、よくぞ痛めつけて命まで奪えるものだ。権力とはかくも怖いものである。ユダヤ人虐殺を敢行した意識に共通する。時代や大衆や権力に迎合することか。人間とは、かくも弱い存在なのだ、だから神を信ずるのか。おそらく、子どもの頃の私も同じようなことを考えたんだと、この地に来て思いだした。
小学校4年生ではなかったろうか。私は、同級生の今岡君とお姉さんに連れられて、島根県津和野町にある「乙女峠」というキリシタン巡礼の地を訪問する会に出席した。津和野カトリック教会から「乙女峠」まで、長い行列を作って、迫害の地「乙女峠」までを、大行列を作って歩く。峠の殉教地に大勢が集まって、大ミサが開かれる。迫害の実態が語られる。
厳冬期、身動き一つできない木箱に一人ずつ入れられて、ただ死を待つ。外に出され、乙女峠にある池の氷水につけられ、「改宗せよ」迫られる。「祈り」だ。殉教していった人々はひたすら祈る。その声を聞いて迫害する側の人間はただ、痛めつけることだけに専念したのだろうか。手がひるんだことはなかったのか、罪の意識にさいなまれたことなかったのか。迫害に耐えて亡くなった人間。仕事・使命とはいえ、ただ痛めつけ迫害したのも人間。今でも、人間は人間を戦争で殺す。なぜだ。人間とはどういう動物なのだ。乙女峠で迫害された少年は、さらし者にされながら、津和野町から、あの長崎の26聖人殉教の地として残っているあの場所まで、見せしめで、素足で歩かされていった。「はりつけ」になって殺されることを望んで歩ききった。小学生の僕は、畏怖を感じていたと思う。僕にはできない。どういう心の持ち主なのだと、随分考えた時期があったように思う。
そのことが、自分の精神構造にも大いに影響していると、ここ生月島に来て感じた。
小学校4年生の冬、萩カトリック教会で、スペインから日本に来て永住され、日本で亡くなられたビエラ神父から、洗礼を受けた。シスターや、ビエラ神父の講話を日常的に聞いた環境で育った。ある日、妹の担任でもあったシスター(妹も、同じ小学校)から
「茂さん、洗礼受けたいですか?」と聞かれた。
「受けたいです」
「だったら、ご両親のお許しをもらってきてください」と。
私は、いつか母に洗礼を受けたいと白状しなければいけないと思っていたし、話したら、怒鳴り返され拒否されると覚悟していた。だから、ずっと言えずに期限を迎えた。シスターから確認された。洗礼式が迫っていた。
「ご両親から許可を頂きましたか?」
「はい、もらいました」と、うそをついた。何も話してはいなかった。だから、困った。
いよいよ、洗礼式1週間前、もっと大変なことになった。
「親同伴で来なければいけませんよ」とシスターの一言。
叱られるのを覚悟して、母に話した。
「今度の日曜日に萩カトリック教会に来てくれる? 洗礼受けるから」
浄土真宗の我が家だから 母は怒鳴り散らし、絶対にダメだというものだと思っていた。ところが、あっさりと母はOKをだした。
「これから、単身下宿して中学校に行くんだ。キリストにすがっている姿勢さえあれば、悪い道に走ることはないだろう」と。 母らしい回答だと思った。
なぜ、信仰したのか。シスターの修道会が経営する小学校で、キリスト教環境にいたことは否定できない。シスターの教義は今から思えば幼いものであったがそれを信じた。カトリック教会では毎日曜日に行われるミサに必ず出席しなければならない。そうしないと罪を犯すと教えられた。そのミサで、神父のお手伝いをする「侍者」という役割をずっとこなしていた。敬虔なクリスチャンとして、ラテン語で行うミサの言語も、今でも覚えて口から自然と発することができる。
高校卒業して、自宅浪人してからも、日曜日は萩カトリック教会で侍者をしていた。高校時分は丸坊主であったが、浪人してからは伸び放題にし、山嵐と呼ばれるほど「ぼうぼう」頭になったある日曜日、ビエラ神父が、全くうまくない彼らしい日本語で
「藤原さん、侍者、これでおしまい、あたまダメね」と。
この一言でやめるまで、ずっと侍者の衣装を毎週着て、神父のそばでお仕えしていた。
それが大学に入り、キリスト教を捨てた。大学紛争まっただ中、いろいろな思想に触れると、幼い教義でしかなかった我がキリスト教は跡形もなくなった。
「転びキリシタンです、私。でも、宗教心だけはあります」そう答えていた。
小学1年生から6年生までメルセス会修道女会が開設した萩光塩小学校在学。中学校2年生から高校3年生までが、イエズス会が経営する広島学院中高校在学。浪人一年目は、自宅浪人しながら、日曜日のみ唯一の外出し、欠かさず、萩カトリック教会のミサ。後はひたすら受験勉強した。目指す大学はいずこも不合格。二浪目は、東京の予備校に出た。四谷のイグナチオ協会に日曜日ごとに行く。熱心なカトリック信者だった。それが、ある日を境に全く、教会に行かなくなった。以来、30年近く過ぎるのか。そのきっかけははっきりしない。大学紛争まっただ中の大学入学。なにがしかの思想的影響を受けたのかもしれないが、それ以上に、児童養護施設の仕事が強烈で、教会などに行く暇すらなく、その暇をくださいというよりも、子ども達がその時間をくれなかったということが正しい。施設は24時間勤務であったし、そういう暮らしを私がしたかったし、大学に行く必要性も感じなかったしという当時であった。
(このブログは、絵画で写生するように、現場であら原稿を書き、その後、ゆっくりできる場面、例えば、今は、新横浜駅前のマグドナルドの二回窓際の席に座って書き直している。すべて移動中の出来事なのだ。)
今思うと、僕のキリスト教は、あの殉教した人になれない自分が、あの方々を、畏怖尊敬した意識が土台になっているのではと思う。その程度の弱い宗教観でしかなかった。
去りがたいが、仕事の時間が近づいてきた。この地の今日の身体の内部に沸いた感覚は、どこかで再び呼び起こすことがあるのだろうか。福祉の現場で感じるものと共通する感覚であるか、それとも異なるものか。絶対に異なるものであるはずがない。私の自覚だ、意識だ。生々しいまま、ブログにはのせまいと思っていたが、何回も推敲して、公開することにした。もはや、このブログは、私の生きている証の日記だから。


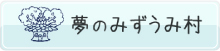 夢のみずうみ村
夢のみずうみ村