北上は 雪。 昨夜 大槌町に児童養護施設を作ることを覚悟した。震災の沿岸部で、仮設住宅で、虐待が絶えないこと、悲劇が深く浸透していること.辛い話の数々を、「おもかげ復元師」の笹原留似子さんが語って教えてくれた。彼女の活動はNHKスペシャルで放送された。ご存知の方も多かろう。「同じNHK仲間だね」と、初対面からあっという間に息統合した。彼女のことを、どう表現したら、イメージしやすいか昨日考えた。ここに失礼を顧みず、彼女にお許しも請わず、勝手に私の一存で書き記す。
彼女は、「ある時は、マザーテレサ、一服吸って藤純子」。
これが私の笹原留似子観。素敵な女性だ。そばにしっかりサポートしておられる菊池さんがまた素敵だ。このコンビで今、東奔西走しておられる。
彼女と知り合ってから、私の人生は大きくUターン現象を起こし始めている。それが何の、どういうU字方向なのかは、どうも、今もってはっきりしない。私の原点、立つ位置、向うべき方向、使命、役割、まとめると存在性といったものが、今朝の北上の水道水のような冷たい水でさらさら、洗い流されているようだし、生きている意義、意味を、風が吹くたびに、木の葉一枚落ちるたびに、地下鉄の人ごみに流されている瞬間にも、自らに投げかけられ、追われ続け、問い続けられている感じだ。それから逃れようとはこれっぽちも思っていないし、むしろそうして流されることを願っている自分がそこにいる。
笹原さんは、震災で亡くなった方々の顔を生前のように復元し、納棺する「おくりびと」である。亡くなった方を、家族の中に、心の奥深く生かす仕事をしていると私は思う。そのことを彼女の本で知った。さらに、直接彼女に知り合うことができて、彼女の話ぶり、語り口、涙、柔らかく暖かい手で、そのことを強く感じとれた。
何か、もっと、あなたに、できることがあるんだよ、と、彼女は伝えている。
虐待児が児童養護施設に避難していることを知ったのは少し前のことだ。かつて20代に私自身が務めていた、東京立川市の児童養護施設「至誠学園」の総合施設長、高橋利一先生から聞いていた。昨夜いたたまれず、久しぶりに電話した。「お兄さん」。学園では児童指導員のことをお兄さんと呼んでいた。何才になっても「お兄さん」「園長先生」なのだ。私は「わしゃ兄さん」とよばれていた。
「お兄さん、とうとう『子ども』に戻りますか」と園長の声。
震災後、初めて入った石巻でショックを受け、動き始めたが立ち止まらざるを得ない事態が起きた。大槌町には2度目。東日本の震災地に最初入った時、目にした風景、ただただ怯えた自分。昨日は、怒りと淋しさ、むなしさに沈んでいた。どうして、ここまで放置されているのか。無残に「まち」が放棄されていいのか。
大槌町の役場では、いろいろ話をしたが、要は「何をしてくれますか」と問われたのだ。やってくる多くのNPO法人。その背景を知って我々の魂と姿勢を再確認した。「住民を依存的にさせてなならない、住民の自立支援を!」という役所の姿勢に納得。夢のみずうみ村ではなく、フジワラシゲル個人がどうするか、覚悟を問われた。
そういう心構えになっていた私に、笹原さんは、ゆっくりしっかり虐待児の話をした。避難先で、周囲のふとした言葉で傷ついた中学3年生の女の子の話。故郷に戻り、亡くなった両親の位牌を抱えて自殺た。、彼女の心を、誰か、ほんのわずかでいい、受け止めてあげれば、命を失わなかったと留似子さんは言った。いっぱい話してくれたが、もう一人娘を亡くしたお父さんの話。
娘の名前を消失した自宅の跡地に、空から娘が見えるようにと、彼女の名前をモニュメントのように作っている写真を見せてもらった。そのお父さんが、娘が描いた絵、灯台を中心に、友達がいっぱい登場するの絵を死後見つけ、それをハンカチにして道の駅に置いたそうだ。娘の心をないがしろにして儲けようとはないごとぞというような揶揄する輩がツイッターで多いことを笹原さんが話してくれた。涙があふれる。「俺だって、おんなじことをする! それを書いたやつ出てこい!」
お父さんは娘さんに会いたいのだ。それだけなのだ。わからないのかよ!
どうして人間はこうして、他人の気持ちをわかろうとしないのか。ツイッターを決して私が使いたくないのは、軽々しく文字が走るからだ。こうした深く考えない輩を社会から追放したいからだ。
当たり前ではないか。私は子どもが自分より早く死に残された親。それも、津波というどうしようもない災害。自分だけ残されたら、このお父さんとおんなじ気持ちになって、娘(こども)に会うための衝動行為としていろんなことをするだろう。そうしないといたたまれないのだ。ほかにわが子を感じ取る手段がないのだ。モニュメントの木を一つ一つ並べながら、泣きながら、お父さんは娘と会っているのだ。素Rがわからないのか馬鹿ども!!。
娘の鎮魂を祈ってハンカチを作ったのだ、そんなことがわからないのか。ハンカチを作って、多くの人たちの手と手に渡ってほしい。それは販売することがベストの手段だ。
娘の存在を知らしめたい、娘を社会に存在させたいという衝動といってもいい。販売することが大切なのだ。お父さんが一人で印刷して周囲の知り合いに配るだけでは、社会的存在にならないのだ。可愛い我が娘が生きていた証をなんとか知らしめたいという素朴な思いなのだ。そうすることでわが子と一緒に語り合い、遊びたわむれ、お茶を飲む、そういう、たわいもない接触を試みたい一心なのだ。私だって同じ立場になれば、このお父さんと全く同様のことをする。
ハンカチの彼女の絵はもっと全国、世界に流れていくといい。販売という手段をとることが、手から手へ渡っていくもっとも効果的な手段である。彼女の遺体は、彼女が大好きだった灯台のそばで見つかったのだと笹原さんが教えてくれた。
岩手の沿岸部に児童養護施設を作る。笹原さんや、大槌、釜石の仲間と覚悟した。足元を見れば、夢のみずうみ村新樹苑を、来年7月世田谷で作る仕事もある。この4か月間近く、ややもすれば無謀ではなかろうかという声を受けながらも私の思いで企画していた事業を、2つ中止して、この世田谷の事業を実現にこぎつけた。わが社会福祉法人評議員会と理事会の仲間と、岡田、吉岡、宮本という部下に感謝したい。こうした厳しいここ4,5か月の間で問われた、法人の資産状況、経営基盤の脆弱さ、加えて、事業意欲旺盛のトップの経営姿勢。いろいろ苦しんで学習をさせていただいた。さて、私はこれからどうするべきか、どうするか。悩み、苦しみ、考えた。
残り少なくなってきた私の人生。終わりがそろそろ見え始めてからの私の人生。子どもたちの仕事に戻ろうかと。いや、加えようかといったほうが周囲に不安を与えないだろう。そうすることにしたい。
自らを鼓舞するために、と同時に、これから始まる支援の輪づくり、具体的には施設建設資金「1億円募金運動」を展開するために こうした思いをブログで公表することにした。自分に後戻りできなくするために、退路を断って、前進するために。
「おもかげ復元師」「おもかげ復元師の絵日記」(いずれもポプラ社)を購入してお読みいただきたい。そこに、笹原留似子さんは居る。会っていただきたい。
実は、明後日、笹原さんが やまぐちの夢のみずうみ村にやってくる。そこで、昨日の覚悟をもっと詰めていこうと約束した。NHKに出演させていただいて得た社会的信用らしきものにすがって、コンビで社会に訴えていこう、自分たちの力で「子どものシェルター」を大槌に作ろう、必ず作ると、昨夜、雪が降り始めた北上側のふもとの料理屋の一室で、仲間6人と決めた。
中村勘三郎さんが昨日亡くなった。私より7歳も若いのに、やりたいことが次から次にあふれてきた方だったのに。私はやりたいことをやらせていただきたい。迷惑を最小限に抑える英知を、今回の苦しい学習体験の中で獲得できた気がする。自分自身に言い聞かせながら、静かに、しかし着実に、仲間と走って行こうと思う。
北上は雪。降り積もるようだ。賢治の故郷に立ち、小学校6年生のとき自らに問いかけた我が身の生きざまを、「アメニモマケズ」の感情を思い出している。
北上駅はまだ雪である。


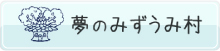 夢のみずうみ村
夢のみずうみ村