「片麻痺になられても、これまでやっていたゴルフができますよ、さあ滅入ってないで、ご一緒にやりましょう」という意図で、軽々しく開始した今大会。今年も昨年同様雨模様の沖縄、久志岳カントリークラブで24名がプレイ。「晴れ男」藤原の面目躍如たるところで、昨年同様、かろうじて雨を逃れて大会を開催できた。参加者のうち、障がいを持たれた方の参加が昨年より少なかったので、正直なところ、私はこの大会を開催する意味を見失っていた。障がい者ゴルフがそれなりに普及している様子であり、様々な障害をお持ちの方が、ゴルフを日常的に親しんでおられる現状を知った。わざわざ、夢のみずうみ村でこうした大会を開く必要はないではないか。前夜祭でお会いした「ジャパン・ハンディキャップゴルフ協会」理事の駒井清さんの一言で私は迷いから覚めた。彼は工事現場9階から1階に落ちて、命は取り留め、右下肢大腿切断にもかかわらずゴルフの名人である。彼の一言が私を変えることになる。
「世界には様々の障がい者ゴルフ大会がある。徐々に疾患別に大会が開かれる傾向になっているような気がする。しかし、『片麻痺』と冠がつくものはどこにもない。やめる必要は全くない。いや、もっと積極的に、『片麻痺ゴルフ』を拡げていこう」という話だ。昨年、片麻痺ゴルフを社会運動として全国に広げるきっかけにしようと、声を高らかに語り、大会を終えたのに、今年は、その広がりを作ることが結果としてできなかった。だから、落ち込んでいたのに、この、駒井さんの一言に元気づけられた。「たとえ、参加者一人になっても、この大会はやろう。そのための資金作りは必死に考えよう」。そう決意を新たにした。
片麻痺の方でなくても、我が夢のみずうみ村ゴルフコンペは誰が参加してもいいのだ。脊髄小脳変性症のKさん。最近、転倒されて、それまでかろうじて歩行器で移動しておられたのに、それができなくなったので、楽しみにしていたこの大会を欠場されるとおっしゃったのである。「何があっても、お連れいたします」、そう申し上げたら、感動して参加を決意していただいた。我々の方が嬉しかった。スタッフと共に現地入りしていただき見事18ホールラウンドされた。2200歩、歩いたとのご報告を聞いた。ただただお見事というほかはない。
パーキンソン病のKさんは、普段、歩行器を押しながら移動されるのだが、カートと杖を使ってラウンド。この大会の特別ルール、ボールの落ちた地点を延長して、カートの脇から打ってよし、を適用されれば、ラウンドがもっと楽なはずなのに、そうしたくないとおっしゃる。正式ルールでいいとのこと。球が落ちた地点まで歩いて行かれて、そこでプレイされた。結果、ハーフで中断された。すさまじい歩行距離である。日頃の夢のみずうみ村での歩行距離も相当だが、ここは目に見えにくい土地の凸凹があっての距離だ。来年は、18ホールを目指しましょうと約束。
私は、最下位だった。昨年初めてゴルフという競技を行い、ハーフでやめていた。しかし、今年は見事18ホールラウンドできた。しかし、途中、昨年同様、球がゲートボール状態、転がる専門で、空中を飛ばないのだ。他のメンバーが、カキーンと快音残してはるか向こうへ跳んでいくのに、私だけ、ちょっと前に転がり、何回も何度も、ちょこまかと打ち続けないとグリーンの上に行かないのである。いささか、飽きてきた。全く面白くない。しかし立場上そういう顔は絶対見せられない。そんな時は掛け声だけ大きくなる。それが逆にむなしさを助長させる。それでも、18ホールを完遂することが目標だったので、それなりに必死。すると、16か17ホール目あたりの、2打目あたりから、なんだか要領をつかめた感じがし始めた。球の下あたりをしっかりと叩けるようになったらしく、ボールが宙に浮き始めた。それが嬉しいのだ。しかし、どうだろう、感触を覚えた気になれたが来年まで持ち続けられるだろうか。間違いなく、いや、おそらく、来年の第3回大会まで、ゴルフには無縁で、1年後のこの大会に、今年同様参加するのだろう。クラブを持っていないので、打ちっぱなし練習場に行くこともできない。練習場ではクラブを貸してくれるのだろうか。行く時間がないこともさることながら、万が一、行ったとしても、今の状態では恥ずかしくて行けそうもない。打ったつもりでクラブを振っても空振り。せいぜい、50、60センチくらい先にコロコロとボールが転がる様を、他人には見せられない。身の程を知っている。だからこそ、この大会は貴重なのだ。ゴルフに無縁の方にも、門は広く開かれている。ハンディーとやらが72で最下位だった私。また来年も出場したいと本心から思えるようになってきた。
自己申告してそれに一番近い人が表彰されるというオネストジョーンという企画がある。58がここのゴルフ場の平均というのか。すべてパーで回るとそのスコアになるらしい。そいう設計なのだ。ちなみに私は153であった。自己申告は138だったのに散々である。
来年、私の結果を参考に、多くの方がやってこられることを願ってやまない


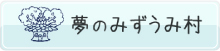 夢のみずうみ村
夢のみずうみ村