埋もれていた 下書きのブログ原稿を 捨てきれずに 再度 原文のまま 当時のまま 恥を忍んで 公開します。あれだけ、時間をかけて書いたものを捨てるに忍びないのです。 この原稿はまもなく2年近く前になるものです。
大槌の子ども達が私のことを「クッソー」と呼んで親しんでくれて久しい。くそじじいになったと我ながら空しくなる。記憶障害が顕著になった。同時に二つ三つのことをすると目こぼし、取りこぼし、置き忘れなどをしでかす。博多駅で切符を買おうとした。カードで買う予定でカードケースを背広のポケットから出したが、「おっと、これは、私用だ現金で買おう」と、カードをやめ、財布をズボンのポケットから出して博多、新山口間の切符を買って、少し、急いでいたかなあ、改札口から新幹線に乗り込んだ。
降りて、施設に戻って、はたと気づく。カードケースがない。どこに忘れたか。車の中、机周辺、背広の中、ポケット、どこにもない。順番に朝から自分がどういう行動したかをたどる。沖縄から帰ってきたとき、空港チェックインはカードでした。間違いなく福岡空港まではあった? 機内に置き忘れていないか?ポケットから、以前、ずり落ちたか、気づかず忘れ物しそうになったことがあった。再現したか? 福岡空港に電話する。忘れ物はなかったとのこと。新山口駅につく。祖のまま。タクシーに乗って施設の戻る。カバン、リュックサック。あるはずがないが、手当たり次第に探しまくる。あるはずがない。カードを使う時はいつ取り出したか。もしかしたら、博多駅でカードで切符を買おうとしたときに、胸ポケットのカードに手を付けたかもしれない。しかし、現金で買ったから、財布には手を付けたけどカードケースには触っていないのではないのか。いや、その時触ったかもしれない。しかし、触って、買うのをやめたらまたポケットにしまうはずではないか。あそこではカードを使っていない。でも、博多駅で落し物があったかもしれない。あらゆる可能性をつぶしていかなければ、いまの私の重度化しつつある記憶障害に対処する手立ては皆無である。「博多駅の落し物預かり所」には2回目の電話であった。戻ること9カ月くらい前、この時も、琉球リハ学院の仕事を終えて、山口に戻るとき、新幹線の待ち時間が長くて、ホームの隅っこのベンチで本を広げ、仕事していた。以前、下の待合コーナーで待っていたら新幹線の出発時間を過ぎてしまった経験があるので、この日は、ホームで待ちながら、本を読んでいた。キャリアバック、リュックサックをベンチの左わきに置き、パソコンケースはベンチ下において、本を読み始めた。何度目かのベル(❓)屋けたたましいアナウンスをもろともせず、集中して読書。何台かの新幹線が出発していった。ハタと気づく。おっ!これだ、乗り遅れるなよ!この列車だ!。キャリアバック、リュックサック、土産袋を持って、新幹線に乗った。席につく。じゃあ、新山口までパソコンで一仕事するか!「あっ! パソコン忘れた!」
新山口駅につく、改札口で、経過を話す。「博多駅落とし物預かり所」に駅員さんが電話。あった! どなたかが落とし物として届けてくださったのだった。すぐ、折り返しの新幹線に乗って博多駅。落し物コーナーまで道順をたどっていく時間の長かったこと。あったパソコン。ほっとした。すぐさま、再度、新幹線に乗って新山口まで。ほっとしたらおなかがすいた。弁当とお茶を買って車内で食べる。キャリアバックなどは新山口駅のロッカーに入れてきているので安心。さあ、新山口到着。弁当くずとペットボトルを車内のゴミ捨てに放り込む。改札口まで向かう。博多からの切符を胸ポケットからとって…。う? ない! 切符がない! いつも胸ポケットに入れるのにない! ズボンのポケット? あるはずない? 様子を目の前で見ていた改札口の3,4名の駅員さん。つい1時間もしない前、パソコンを忘れたと大騒ぎして、博多まで新幹線㋑飛び乗っていった同じ、髭づらのくそじじい。またかよ!?という感じ。「多分ですが、切符を早々と手に持っていたので、弁当くずと同時にくず入れに捨てた可能性があります」と白状。駅員さん。「先ほどのことから、あなたが博多まで切符を買われていき、戻ってこられたことは察しがつきますが、有価証券です切符は。本来お手元になければ、再度、買って頂かなくてはいけないのですが、今回は特別です」と大岡裁判。助かりました。JRさんに感謝いたします。しかし、しかし、これで、話が終わらないのです。
この足で山口デイに戻り、スタッフに報告。「じゃあ、この先の予定を相談させてください」と言われる。手帳だ! 手帳がいる。命の次に重要な手帳。私の日程を管理している絶対的手帳。分厚い、汚い、システム手帳。ない! どこを見てもない。学校に忘れてきたか? 電話して、学校の私のデスク周りに捜査の依頼。ありませんの電話。手帳を学校で広げた気がするが、もしかしたら錯覚で、浦安デイで広げていたかもと思い、浦安デイに電話。無論ない。???。もしかしたら、最初の博多から帰るときの新幹線で、パソコンがないといって、リュックサックやカバンを家探ししている時に、新幹線の空いていた席をいいことに手帳も出してそのままにしていたなんてことはないかなと。再度博多駅の今度は新幹線内忘れ物センター(実際は先の駅の忘れ物と同じようであるが)に電話してみる。列車発車時間を伝える。「ありませんね」の反応。がっくり。電話を切ろうとすると、「その新幹線は、東京行きですからJR東海の忘れ物センターに電話されたら」と優しい一言。電話した。「わーっ! あったあ!」。喜びというより、情けなさ。この、一連のわ忘れ物騒動。情けないに尽きるし、自分の記憶力低下、アルツハイマー病の前駆症状と自己判断したくなる状態。恐ろしくなった。
こうした、なかでの、
毎日、ブログを更新するという習慣をつけたいなと思っています。 それは、私のようなもののブログでも、「更新していないねえ 元気なのかい?!」と お声をかけてくださる方が、一人二人あったからです。本当に、嬉しい一声でした。死んだように沈んでいるホームページを輝かせるようにしなくてはと、責任者として痛感しております。動きます。そのためには、まず、我がブログを積極的に更新することは最低条件です。頑張りますね。
人間は、一人一人、心の内に「意思の水」の湧きでるところがあります。生きている証しです。その水は、「意思のせせらぎ」となって周囲に注ぎます。いきているヒト誰もの内面で起きている現象です。さらに、ヒトは、そのせせらぎを、「事なす(何かをする)」たびに堰(せ)き止めながら、大なり小なりのダムを作って、放流し、自家発電することによって、エネルギーを自家発電します。この自己発電エネルギーを使って、生活します、生きていきます、成長していきます。堰き止める水の量が、どれだけ多いか少ないか。ダムの容量がどのくらいか千差万別です。こうした、夢の湖と名付けた「自分湖」、「自分ダム」「自家発電」「自分電気」というイメージを、イラストにして、講演会では随分と話してきました。
ふと、今日思ったのです。我がダムの大きさは、黒部ダムみたいなのか。それとも、私の小学校の遠足で行った阿武川ダムなのかと。小学3年生頃に見たダムの放流は感動しました。71歳にまもなくなろうとする私の自分湖は、水を蓄えているのか、ダムは、かつて見た阿野黒部ダムの放流のごとくには電気を生み出さないだろう。どのくらい発電するのかなあ。流れ出した水は、川となって海に注いでいくのだろうか。
ブログを休んでいるうちに、夢の湖の水が大海に流れ出ていくことに気付かずにおりました。海は広いな大きいな。行ってみたいなあ、今まで行ったくに(場所)にも、めったに行けなかったくに(場所)にも、まだ行ったことがないくに(場所)にも。そこにもかしこに、いたるところ(場所)に、知った人、知らない人、まだまだたくさんあること、それを、今になってまた、激しく、優しく、意思のせせらぎを漂い流れながら、ある日は、自分湖の真ん中で、手漕ぎボートでゆらゆらしながら思うのです。海は広いな大きいな。
ホームページも古く、手が入っていないぞとお叱りを受け、君のブログも古い!どうなっているのかねと、重ねてお怒り。わかっておりながら、日々ながされ、まずいまずいと叫びながら、一心不乱衣にあちこち渡り歩いております。押し流されていますが、まだ、しっかり自分を保っている自負だけは失わないようにしております。それだけ、助けられているという実感が相当深く強く私に返ってきていることも承知しております。
線香花火にあちこち火をつけて回っている感じです。一瞬燃えて消えたら、藤原マッチを寒風吹きすさぶ中で必死に火をつけて線香花火を燃やし、その場を離れ、追われ、また次の場所で線香花火を取り出し、説明し、火をつけるという仕事、暮らしぶりです。線香花火を、ロケット花火にするつもりはありませんが、みんなの力を活用しながら、仕掛け花火をこしらえたい思いです 確実に、夢のみずうみ村の土台をさらに強化する役目を果たしていこうとして、がむしゃらにやっております。動き回ればいいというものでもなく、考えを、スタッフと共有しながら、スタッフ個々と共感し合いながら、夢のみずうみ村を作っていきます。必ず、素敵な花火大会を各所で開きます、スタッフたちが自分達の手でです。
今、私が、夢のみずうみ村で取り組んでいますのは、①実施しているプログラムがどういうで中味・どんな効能があるかを、8つの力(自分力)を使って、示そうとしています。利用者さんが実施しておられるプログラムは、どういう内容が含まれていて、どういう効能があるかを視覚化し、施設内のそれぞれ、プログラム実施場所でお示し掲示するという作業です。
自分力、8つの力は、「生活行為力向上」の拙著でお示ししておりますのでここでは、恐縮ですが省略させていただきます。難しくは考えられないように、さながら、出来上がったイメージは「仙台の七夕」のごとく、にぎやかに、ひらひらと垂れ下がった短冊よろしく、効能書きが読み取れるという趣向です。防府のデイサービスのメンバーが鋭意取り組んでいます。見事です。あと1カ月もすれば お披露目できるでしょう。お越しくださいませんか。
登校したつもりが、下書きに保存したままになっておりました。情けなく恥を忍んで こう聞いたいます。そういう公開が、これから、いくつか続きます、なぜならば、せっかく、時間を割いて文字化したのに、文字たちが、心が泣いている気がして、自分委許せなくなって、身勝手に。公開いたします。
ある日の、しかも、相当?前の 私のブログです。見捨ててくださいませ。
随分とブログが空きました。予想外に このブログをご覧になっている方がいらっしゃることを あちこち移動して中でふと、Aさん、Bさんから、Eさんくらいまで、続けてお声かえ頂くことがあり、昨今のIT事情に疎い私としては、うれしいようなつらいような感じがしております。
年賀状を例年500枚頼み、これを正月元旦に書くのが恒例になってしまっていた一時期から、写真入りをやめて手書きコピー式にして以来、年末31日の夕刻までには投函できるような感じでやってきました。ところが、一昨年、昨年と賀状差し控え連絡がすさまじくあり、とうとう、今年、私は年賀状をほぼ100枚、出さない状態になりました。私自身、本年年とって71歳。当然の状況が回りに怒っているのだと思います。そこで、既に、「来年の年賀状だして終わりにすること」を決めました。通常はがきでそれを出すか、年賀状にするかは考えますが、そう決断しました。また、今年も、年末に近づくと、相当、多くの方々から賀状控えるはがきが来ると予想されます。
そうした一方で、夢のみずうみ村のこのホームページの「ていたらく」を多くの方から指摘されております。介護保険改正で、」大規模減算、大幅減産の実施とその対応で、他の類に盛れず、経営に苦心しております。本当に、厳しいです。それは、無一文の私が、NPO法ができ、意志あるものに銀行がお金を貸す時代になったこと。1円株式会社という言葉が世に踊った時代背景が生まれたこと。そこに、おっちょこちょい藤原茂が烈火のごとく走り回ってしまったこと。それが、お金がないのに、銀行さんがっ貸してあげるよとおっしゃらべ、喜んで借りて、これだけの事業を始めてしまったことにつきます。介護保険の改正で、単価がこうして暫時下げられていくとは、開設時、西暦2000年、NPO法ができたときは全く予想だにしませんでした。同時に、福祉とリハビリのことしか知らない私が、経営を知る由もなく、「いいことは、どんどん社会に広げよう」という視点に立って、結局は借金の中で事業計画を展開してきました。このいい加減なトップによくぞ職員諸君がついてきてくれたと思います。愛想をつかして離れていった職員ももちろんいます。
昨今、記憶力低下が著しく、周囲の職員諸君に支えられながら業務遂行する無様な姿である。 いつまでも 今も立場では仕事が続けられないと日夜反芻している。そんな中で、このブログが長く更新されていないこと。古い、編集中の下が気が出てきたことで、「下書き」(2017年11月)を公開することにした。1年くらい前の話である。
大槌の子ども達が私のことを「クッソー」と呼んで親しんでくれて久しい。くそじじいになったと我ながら空しくなる。記憶障害が顕著になった。同時に二つ三つのことをすると目こぼし、取りこぼし、置き忘れなどをしでかす。博多駅で切符を買おうとした。カードで買う予定でカードケースを背広のポケットから出したが、「おっと、これは、私用だ現金で買おう」と、カードをやめ、財布をズボンのポケットから出して博多、新山口間の切符を買って、少し、急いでいたかなあ、改札口から新幹線に乗り込んだ。 降りて、施設に戻って、はたと気づく。カードケースがない。どこに忘れたか。車の中、机周辺、背広の中、ポケット、どこにもない。順番に朝から自分がどういう行動したかをたどる。沖縄から帰ってきたとき、空港チェックインはカードでした。間違いなく福岡空港まではあった? 機内に置き忘れていないか?ポケットから、以前、ずり落ちたか、気づかず忘れ物しそうになったことがあった。再現したか? 福岡空港に電話する。忘れ物はなかったとのこと。新山口駅につく。祖のまま。タクシーに乗って施設の戻る。カバン、リュックサック。あるはずがないが、手当たり次第に探しまくる。あるはずがない。カードを使う時はいつ取り出したか。もしかしたら、博多駅でカードで切符を買おうとしたときに、胸ポケットのカードに手を付けたかもしれない。しかし、現金で買ったから、財布には手を付けたけどカードケースには触っていないのではないのか。いや、その時触ったかもしれない。しかし、触って、買うのをやめたらまたポケットにしまうはずではないか。あそこではカードを使っていない。でも、博多駅で落し物があったかもしれない。あらゆる可能性をつぶしていかなければ、いまの私の重度化しつつある記憶障害に対処する手立ては皆無である。「博多駅の落し物預かり所」には2回目の電話であった。戻ること9カ月くらい前、この時も、琉球リハ学院の仕事を終えて、山口に戻るとき、新幹線の待ち時間が長くて、ホームの隅っこのベンチで本を広げ、仕事していた。以前、下の待合コーナーで待っていたら新幹線の出発時間を過ぎてしまった経験があるので、この日は、ホームで待ちながら、本を読んでいた。キャリアバック、リュックサックをベンチの左わきに置き、パソコンケースはベンチ下において、本を読み始めた。何度目かのベル(❓)屋けたたましいアナウンスをもろともせず、集中して読書。何台かの新幹線が出発していった。ハタと気づく。おっ!これだ、乗り遅れるなよ!この列車だ!。キャリアバック、リュックサック、土産袋を持って、新幹線に乗った。席につく。じゃあ、新山口までパソコンで一仕事するか!「あっ! パソコン忘れた!」 新山口駅につく、改札口で、経過を話す。「博多駅落とし物預かり所」に駅員さんが電話。あった! どなたかが落とし物として届けてくださったのだった。すぐ、折り返しの新幹線に乗って博多駅。落し物コーナーまで道順をたどっていく時間の長かったこと。あったパソコン。ほっとした。すぐさま、再度、新幹線に乗って新山口まで。ほっとしたらおなかがすいた。弁当とお茶を買って車内で食べる。キャリアバックなどは新山口駅のロッカーに入れてきているので安心。さあ、新山口到着。弁当くずとペットボトルを車内のゴミ捨てに放り込む。改札口まで向かう。博多からの切符を胸ポケットからとって…。う? ない! 切符がない! いつも胸ポケットに入れるのにない! ズボンのポケット? あるはずない? 様子を目の前で見ていた改札口の3,4名の駅員さん。つい1時間もしない前、パソコンを忘れたと大騒ぎして、博多まで新幹線㋑飛び乗っていった同じ、髭づらのくそじじい。またかよ!?という感じ。「多分ですが、切符を早々と手に持っていたので、弁当くずと同時にくず入れに捨てた可能性があります」と白状。駅員さん。「先ほどのことから、あなたが博多まで切符を買われていき、戻ってこられたことは察しがつきますが、有価証券です切符は。本来お手元になければ、再度、買って頂かなくてはいけないのですが、今回は特別です」と大岡裁判。助かりました。JRさんに感謝いたします。しかし、しかし、これで、話が終わらないのです。 この足で山口デイに戻り、スタッフに報告。「じゃあ、この先の予定を相談させてください」と言われる。手帳だ! 手帳がいる。命の次に重要な手帳。私の日程を管理している絶対的手帳。分厚い、汚い、システム手帳。ない! どこを見てもない。学校に忘れてきたか? 電話して、学校の私のデスク周りに捜査の依頼。ありませんの電話。手帳を学校で広げた気がするが、もしかしたら錯覚で、浦安デイで広げていたかもと思い、浦安デイに電話。無論ない。???。もしかしたら、最初の博多から帰るときの新幹線で、パソコンがないといって、リュックサックやカバンを家探ししている時に、新幹線の空いていた席をいいことに手帳も出してそのままにしていたなんてことはないかなと。再度博多駅の今度は新幹線内忘れ物センター(実際は先の駅の忘れ物と同じようであるが)に電話してみる。列車発車時間を伝える。「ありませんね」の反応。がっくり。電話を切ろうとすると、「その新幹線は、東京行きですからJR東海の忘れ物センターに電話されたら」と優しい一言。電話した。「わーっ! あったあ!」。喜びというより、情けなさ。この、一連の忘れ物騒動。情けないに尽きるし、自分の記憶力低下、アルツハイマー病の前駆症状と自己判断したくなる状態。恐ろしくなった。
こう「下書き」の症状は、今でも時折顕著に出現する。もはや、1㋔カ月以上前の話ではあっても、こうした周囲に気が回らない、気づかない、物忘れ、不注意等、自分がどうしようもない。何を為すにもおぼつかない自分。終活に入ろうと決意し始めている。当面、まもなく70歳になる。それが 終活の スタートである。
2013年4月11日に始めました「子ども夢ハウスおおつち」は、最後の一年間を親の会に業務委託して運営を継続してまいりましたが、本年3月末日で終了いたしました。これをもって、「子ども夢ハウス大槌」の全事業が終焉いたしました。この間、多くの方々にご支援を賜りました。皆様の「お志」で、今日まで継続してこれました。衷心より御礼申し上げます。
振り返ってみますと、震災後2年後に始めた意義は大きいことであったと強く感じます。復興の過程の中で、心のよりどころを見失いがちになりそうなタイミングがその時期ではなかったかと、他の災害事例、若者の失踪事例の報道などから情報を得て感じるのです。「子ども夢ハウスがなかったら、〇〇〇でしたね。」という声を、開設以来、本当にたくさんの方々から伺いました。「すりきず公園があってよかった」という声も、ずいぶん伺いました。今もなお大槌に、あれだけの広さで、あれだけの内容の公園は身近にありません。
現在、安渡地区は復興住宅も盛り土の上にできた高台に立ち、子どもたちも仮設住宅から新しい家に引っ越しました。旧子ども夢ハウスの借家は、そのままに、かの場所にあります。すりきず公園のあった場所にも家が建ち、面影は全く消えました。しかし、すりきず公園裏山の神社の斜面に作った、スライダーまで横から昇っていく坂道に、子ども達が滑り落ちないようにと、ボランティアの皆さんが作ってくださった小さな木の柵が、しっかり残っているのです。間違いなく、ここで子どもたちがはしゃいでいたという証拠、記念物体があるのです。木製の小さな作りですが、朽ちないことを願い続けます。それ以外には、安渡公民館も、安渡小学校も、みな新しくなり、思い出がすっぽりと消えた感があります。職員として最初から頑張ってくれた吉山君とマイナス4度(山瀬の風が吹きすさび、体感温度おそらくマイナス10度)の中、二人で夜遅くまで細々と、鼻水すすって作ったクリスマスイルミネーション。遠くの方からも見えるようにと、二人で必死に高い木々の上にひっかけようとして齷齪した神社の樹木は健在です。3.11に夜空に光る風船を飛ばした場所には、水産加工場が建ち、面影は全くありません。 復興したのです。
何ができたか、何を私たちはやったのか、これでよかったのか、もっとやりようはあったのではないか。思いは複雑です。ただ、必死に、目の前のことをやってきたにすぎないのです。計画性はあるようでなかったので、ご批判も受けました。賛否両論、いろいろのご意見を賜りました。この場で御礼申しあげます。皆様の、ご支援、ご意見、お気持ちがなければ、ここまで続きませんでした。この紙面をお借りして御礼申し上げます。
親の会の皆さまには、新しい場所に移転しての運営を1年間していただきました。まる投げ状態でお願いいたしましたが、心をしっかりつないで頂き、あたたかく、しっかりと夢ハウスを受け継いでくださいました。本当にありがとうございました。この場をお借りし御礼申し上げます。
スタッフとして、最初から最後まで頑張ってくれた横ちゃん。通っていた小1のK君のお母さん。職員になって頑張っていただきありがとう。大きいお兄さんとして夢ハウスに時々通っていた当時高1のT君。その後、職員になってくれて、最後まで子どもたちを優しく見守ってくれましたね。本当に感謝です。スタッフの皆様、本当にご苦労・ご心痛をおかけしました。素敵な思い出がいっぱいできました。子ども達と一緒に、成人式、結婚式、その他、何でもいいから幸せのおすそ分けをする会合を作って会いましょう。
子ども夢ハウスを始めるから転勤してくれないかという勝手な要望に即答で大槌に移り住み込み、子どもたちの兄貴分、安堵地区のお年寄りのアッシー、拠り所、駆け込みハウスの住人となってくれた吉山周作君。今は、夢の村みずうみ村新樹苑(世田谷区)のデイサービスの責任者として引き続いて頑張ってくれています。感謝、感謝です。
事業報告、決算報告は、間もなく、ホームページにて掲載させて頂きます。本来なら、個々の寄付者の皆様には、個別に御礼とお知らせをすべきでありますが、こうした方法に替えさせていただきますことをお許しくださいませ。ここに、「子ども夢ハウスおおつち」最終終了のご報告のみとさせていただきました。
子どもたちの将来の発展、ご家族、ご支援いただいた方々のご幸福をお祈りしながら、この報告をおえさせていただきます。本当にありがとうございました。
夢のみずうみ村 代表 藤原茂
美空ひばりの歌である。「りんごの故郷は 北国のまち」で始まる。流れ流れて昨夜遅く 新山口駅前のホテルに泊まった。朝食、リンゴが細かく刻まれて提供されている。同じチェーン店の東北新幹線、北上駅前の同ホテルでしばしば刻まれたリンゴを食べた。今日、大槌の子どもたちの顔がリンゴの中に出てきた。不思議だ。春休みの28日、29日に、泊りがけで、秋田県境の西和賀に雪合戦サッカーをやりに出かけた。夜中1時前、皆が就寝した後の深夜に、こっそり大風呂に4人組で入った女の子たちを集め説教した。「ルールを守れ」と。後悔だ。言わなければよかった。大人のエゴではないのか、子どもの自由、のびのびを保障しようとするお前(私)の理屈に反するではないか。リンゴを食べながら悔やまれた、子どもたちに謝らねば。「リンゴの故郷」を聴くと、必ず涙がにじみ出る。私の故郷は、リンゴの故郷、北国のまちが しっかり加わってきた気がする。山口県でも島根県境でリンゴは取れる。しかし、微妙に味が違う。ゆっくりかむ。〇〇が違う。〇の中に何が入るか文字化できない。故郷はいくつ人間にはあるのだろうか
表題の文書を ご寄付いただきました全国の方々に以下の文書を郵送させていただきました。ご寄付いただいた当時のご住所に文書を郵送させていただきましたが、返送されたものも多数あり、この場をお借りして、お知らせ並びに御礼を申しあげたいと存じます。同時に、匿名でご寄付いただいいた方々も多数あり、重ねてこの場で御礼申し上げたいと存じます。ありがとうございました。
郵送文書 (原文のまま)
2017年3月1日
子ども夢ハウス1億円募金にご支援くださった皆様
夢のみずうみ村 代表 藤原茂
「1億円募金運動終了」と「子ども夢ハウス」のこれから
厳しい寒さと、寒暖差が続く今日この頃でございます。沿岸部の大槌でも大雪の日があり、雪遊びに子どもたちは興じました。いつもと変わらぬ厳しい海風が吹き荒れる毎日が続いておりますが、子どもたちはいたって元気です。皆様におかれましてもご健勝のことと拝察申し上げます。
日頃よりのご報告を全くいたしておらず、「子ども夢ハウスだより」も滞りがちの中、唐突に、このお知らせをいたします非礼を、まず、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。
開設以来、夢ハウスの管理者として、寝食を賭して活躍してくれた夢のみずうみ村職員、吉山周作君が、社内結婚で結ばれ、首都圏の夢のみずうみ村(世田谷新樹苑)に転勤いたしました。そのあとを、若い男性職員2名を新規雇用し、吉山君時代から頑張るお母さん職員2名と計4名で奮闘しながら運営を続けております。
振り返ってみれば、4年前の2月頃、納棺師の笹原留似子さんと知り合い、彼女の「駆け込みハウスが必要だ」の話に触発され、衝動的に「子ども夢ハウスおおつち」を開設しました。当初から、助成金に頼らず、募金活動のみで施設運営をする判断をし、1億円募金は始まりました。
募金は、5期にわたり、第1期、子ども夢ハウスおおつち。第2期、夢ランド(すりきず公園と命名)。第3期、スープや夢結び(車による移動販売)。第4期、がやがやハウス(就労支援事業所)。第5期、エルダー旅籠夢長屋(介護付きホテル)と、段階的に資金を集めて事業展開する計画でスタートいたしました。
本日まで、総額52,253,226円という素晴らしい運動となりました。本当に感謝申し上げます。
募金運動を実施する責任主体は、社会福祉法人夢のみずうみ村が行い、運営資金一切を募金で賄うことを条件に、法人事業として開始いたしました。「夢のみずうみ村」は、介護保険事業のみを行う法人であり、銀行からの借り入れで運営を行う実態の中での大槌事業の開始ですから、法人会計から大槌事業の負担をすることは当初より不可能でしたので、大槌に関する全てを寄付金で賄うことで動き出した次第であります。
1.子ども夢ハウス開設と運営資金
募金運動のおかげで、子ども夢ハウスは、大槌町安渡地区に7LDKの民家を借りて駆け込みハウスを開設し、近隣に「すりきず公園」も作り、遊び場のない子どもたちの格好の暴れ場所となりました。(1億円募金の第1期事業と第2期事業の実現)。借家借り上げ費、すりきず公園づくり費用、子どもたちの日常プログラム運営費、行事費、イベント開催等のプログラム費、山口デイサービスから運んできたワゴン車の車両管理費、光熱費、さらに、人件費等々のランニングコストも、子ども夢ハウスに掛かる全ての経費を募金で賄わせていただきました。
そんなある日、「募金は、事業費のみに使っていただき、事務費(人件費、ランニングコストなど)に使うことはやめていただけないか」というご意見を承りました。助成金を受けない覚悟で始めましたので、「運営資金は募金しかなく、子ども夢ハウスにかかわるすべての経費を賄わせていただかざるを得ないのです」と、ご理解を求めましたがご納得いただけませんでした。しかし、そのご意見を頂いたことによって、必要な経費に絞って運用する覚悟ができ、公正に今日までやってこれたと思っております。この報告をご覧になった中にも同様なご意見をお持ちの方がおられるかもしれないと思い、ここに明記させていただき、なにとぞ、ご了解を賜りたくお願い申し上げる所存でございます。
子ども夢ハウスの5期にわたる事業計画は、募金が一定の目標金額に達して、はじめて事業を開始展開するというものでしたので、運転資金は別建てにしなければいけないことは自明の理でした。社会福祉法人理事長の藤原(当時)が、「全て寄付金で運営するから法人には迷惑をかけない」と宣言し、独断専行型で始めました。夢ハウス事業にかかる経費は、家賃、人件費負担が大きく、徐々に、社会福祉法人に負担をかけ始めました。それを、職員、理事各位のご理解とご支援で、乗り切りながらやってまいりました。一方、介護保険事業の単独運営事業を行う当法人にはおのずと限界があり、国の制度改正が行われる度に、単価改正も行われ、収入減による不安定経営を強いられる経営実情下での大槌事業でした。この間、職員各位には、賞与不支給の現実を呑み込みで頂きながら、大槌事業の法人支出を行うという不測事態をもたらしたりしました。しかし、子ども夢ハウスの運営資金の主体は、今日まで絶え間なく続く募金活動であり、ひとえに、募金活動してくださいました全国各地の多くの皆様のお志であります。
2.子ども夢ハウスを、「公的認可事業に」から「新天地に移転へ」
こうした運営状況を打開し、長期的に安定した運営体制を作ろうと考え、子ども夢ハウスを公的認可施設に申請しようと考えました。この段階で重大なことが判明しました。借りていた7LDKの民家が建築基準を満たしていなかったのです。よって、公的支援の申請ができないことが判明しました。
混乱していたところに、延べ面積が今より3倍近く大きく、家賃も安い住宅が出てきました。大槌町内移転ですが、施設があった安渡地区内ではないので大変な決断を迫られました。すでに施設近隣の地域の住民の方々と密着しており、子どもたちの原風景にもなっているこの建物から移転することは考えにくい選択肢でした。
しかし、経済的支援を受けられない建造物であるという重大な問題点は、いかんともしがたかく、苦渋の決断で移転決定。子どもたちみんなの力を結集し、現在の大槌町大ヶ口に大移動を図りました。この決断が、正しかったかどうか、今もって、意見の分かれるところとなりました。
3.最近の子ども夢ハウス
本来、子ども夢ハウスには2つの機能があります。第一の機能は「放課後学童の運営」、第二の機能は「駆け込みハウス」です。
震災直後に、面影復元師の笹原留似子さんが訴えた「自ら命を絶とうとするような心境の子どもたちの話を聴く場、逃げてくる場所、何事かある場合の緊急避難所をつくろう」といった必要性は、震災後6年過ぎた今ではもはやなく、駆け込みハウスとしての役割は終えたのではなかろうかと、笹原さんと私で共有確認いたしました。
学校に行けない子どもたちは、新しく移転した夢ハウスにもふとやって来ます。以前からそうでしたが、夢ハウスしかこられなかった子どもは、やがて少しずつ通学できるようになります。不登校期間が長くなった子どもは、学習面で著しく遅れる心配をしはじめ、学習塾に午前中行き、午後夢ハウスに戻ってくることができるようになります。家からまったく出られなかった子どもが夢ハウスには来て、ここを踏み台にする実態があります。
夢ハウス開設当初は、震災後2年近く過ぎているのに、大槌に自由な遊び場はなく、学校と仮設をスクールバスで往復する毎日。たまり場のない子どもたちの必要な空間として、子ども夢ハウスはその役割を果たしてきたと思います。最近でも、夢ハウスにやって来て、することはといえば、部屋の中で、ドッジボール、卓球、新時代ベーゴマ遊びや人生ゲーム、料理、さらには、新しく夢ハウスの裏庭に作った「第二すりきず公園」でサッカー、バスケット、滑り台に興じます。しかし、「学ぶ」ことを捨てた施設ではありません。広い家の中に学習室も常設し、放課後はまず宿題をしてから遊ぶ習慣化は達成できました。不登校の子どもたちは、個人差はあれ、戻るべき学び舎にやがて戻っていくワンステップとしてここを利用します。子ども夢ハウスは、しっかり、社会資源の一つとして大槌町での存在を示してきたと実感します。
4.子ども夢ハウス事業、継続か否か、決断の時
大槌役場、教育委員会から、放課後の子どもたちの支援をどうするか声かけがありました。関係機関は、放課後デイを行っている、夢ハウス含む3施設。学習塾1施設。読み聞かせ1施設。教育委員会、障害福祉課などです。これからは、分散して支援するのではなく、各団体が連携し、学校生活と放課後の流れを作り、共同して事業展開しようという動きです。最近では、放課後、集団下校の集会場にスタッフがお迎えに行き、一緒に夢ハウスに帰ってくる子もいます。夢ハウスに来なくても、復活した野球やサッカーの活動をやったり、フリースクール形式の学習塾に行ったりと、少しずつ活動の選択の幅が生まれ、子ども夢ハウスの存在意義が変わりつつある背景が見えてきました。震災発生から6年目に入り、火急的な支援から、永続的支援に転換する時期に入った被災地に共通する課題かもしれません。大震災でショック昏迷状態が起き、多くの助けを必要した被災直後の支援。その後の緊急復興支援。2年後から開始した子ども夢ハウスは、継続的支援と呼ぶべき支援といえそうです。子ども夢ハウスができた復興2年後も、大槌に自由な遊び場はなく、学校と仮設をスクールバスで往復する毎日。たまり場のない子どもたちの必要な空間として、子ども夢ハウスの支援は不可欠でした。
こうした様々な被災地での支援活動は復興6年を経て変わりつつあります。活動を終了していく団体も目立ちます。支援活動をどのように展開するか、各団体が過渡期に入ったといえます。行っている活動を、永続的支援という形で提供すべきか否か、決断する段階に来ているのです。
子ども夢ハウスでいえば、4年間続けてきた活動を、ここで新たに組織固めして、永久的支援に展開すべきか否か、決断する時になりました。社会的必要度、運営人材、経済的側面の3つの要点で決断を迫られています。
開設当時訪れた子どもたちの顔ぶれ、利用期間、利用内容・状況は(微妙に)異なりますが、どのお子さんにとっても、子ども夢ハウスがなかったら、その成長過程はどうなっていただろうかと案じさせるほど、一人、一人に、素敵な影響(成長)をもたらしたと思います。ご支援いただいた皆様方のお気持ちは、素敵にこの地のこの子どもたちの中に育まれたと確信いたします。さて、この先です。
大槌町では、昨年9月23日、小中一貫校「大槌学園」を開校し、仮設小・中学校を廃止しました。さ来年度4月には、学童保育所を併設することになっています。こうした背景下で、我々が震災2年後から行ってきた子ども夢ハウスの支援は、まだ必要な存在なのであろうか、大槌の子どものための支援社会資源はそれなりに充足されてきている、それでも、社会資源の一つとして存続運営していくべきか。いや、いつまでも支援の輪の中にあるのではなく、地域に委託委譲し、地域社会を育てることも重要ではないのか。いや、それは時期尚早、支援はまだ不可欠なのではないか。こうした葛藤は、それぞれの支援団体が行っております。いろいろな支援団体、人が大槌から離れ、去っていきました。一方ではそれこそが復興の証です。復興が着実に進んでいるのです。
5.1億円募金の終了と「子ども夢ハウス基金」の設立
今後の子ども夢ハウスの運営は、町内有識者や利用しておられるご父兄代表で構成するを「子ども夢ハウスおおつち郷親(さとおや)の会」(当面、無認可)を設立することにしました。皆様からの募金残額は、今日の時点で1千万円余あります。これを基金として、「子ども夢ハウス基金」を設けます。異土の社会福祉法人が運営してきた活動を、地元の皆様、ご父兄で構成する「里親の会」に移管できることは素晴らしい活動の転機であると感じます。よって、1億円募金活動は、本年3月をもって終了させていただきます。
これまでの、ご寄付の使途につきましては、別紙に決算書で報告させていただきます。残金をすべて、子ども夢ハウスの活動に使わせていただきますので、この会に、全額移譲することを、ご寄付いただきました皆様に、勝手ながらご了解いただきたいと存じます。皆様のご意思が、最後まで、しっかり、おおつちの子どもたちのために使われることを見守らせていただきます。
この基金で、おそらく最大1年間程度は事業を継続し、地域の社会資源として、他の事業者と協同し、子どもたちの支援を行うことが可能だと思います。皆様からのご寄付の全てを最後まで子ども夢ハウスおおつちで使わせていただきます。
当初より、事業費のみならず、事務費も含め、子ども夢ハウスおおつちにかかわる全額を、皆様からのご寄付で賄わせていただきました。丸4年間の活動を皆様のお志が、この活動を生み出し支えてくださいました。
本当に、本当に、ありがとうございました。
全寄付者の方々に、この文書をもって、経過報告と、勝手ながら、今後の展開にご了解いただいたものとさせていただきたいと存じます。
よろしくご高配のほどお願い申し上げます。
追記
子ども夢ハウスを、開設当初から長きにわたって追跡報道されてこられたNHKが、これまでの4年間分を総括した報道を以下の日程で放送するとのお知らせを頂きました。
これまで、4年間、子どもたちの成長とともに番組を作っていただき、東北地方では地方発ドキュメントとして何度か放送されました。NHKのスタッフ、赤上・大渕・原の3氏と藤原を含めた4人は「ヨンタクロース」と名乗り、クリスマスには、東京、盛岡と、子ども達から注文されたプレゼント買いに奔走する仲間になってしまいました。
この放送をぜひご覧いただき、ご寄付いただいた皆様方の「熱い志」が随所に生きていることを実感していただけるものと信じます。皆様が、この画面に登場する子ども達を育んでくださったのです。1億円募金活動にご協力くださった皆様、おひとりおひとりにお声をかけることができませんが、画面から子どもたちのメッセージをつかんでいただくことができると確信します。組織・団体も併せて、総勢900人の方々のご支援に、重ね重ね感謝申し上げます。画面に登場する子どもたちやご父兄ご家族。登場していない子どもたちやご家族のご協力にも会感謝します。
末尾となりますが、この場をお借りして一言、お礼を申させていただきます。身内ともいえる夢のみずうみ村フランチャイズの施設の経営者、管理者、職員の皆様方。夢ハウスの激動・激流に激しく共に葛藤した社会福祉法人の理事・関係者。とにもかくにも、大槌の子どもたちを、遠方においても見守り続け、支えてくれた夢のみずうみ村全職員の皆さん。ありがとうございました。
1月29日 奈良県天理市の「陽気ホール」で開催。盛況だった。登場された順に紹介。1番手は「チーム Yasu の取り組み~四肢麻痺を乗り越えて」。講師 名倉 康友さんとは二回目の出会いであった。「歌手のつんくさんのように話ができませんが『伝の心』というパソコンを使って文章を書き、奥さんがそばでマイクで読まれ、発表されるというスタイルが、今日も見られた。明石大橋走破のビデオが圧巻である。2回目の拝聴であったが、やはりすごい。チームYasuのメンバーが 車いすを抱え、大橋のてっぺんから瀬戸内海を望む場面。橋の上の通路は、車いす目線では見えない高さなので、みんなで「せーのー」で車いすを抱え上げ、メンバーの男性の「キープ!」の一声があがる。名倉さんに、明石大橋のてっぺんからの景色を、他の人間同様にみて頂こうとする必死のチームの面々が、車いすを持ち上げ保持しているのだ。ただただ感動である。 夢のみずうみ楽会は「障がいを持ち、いったんはあきらめ沈んでおられる方々が、どっこい、『障がいを持ったからこそ、こんな素敵な人生が待っていた』と実体験を語られる会である。
2番手は 奥田優子さんと出口孝行さん。優子さんは、以前、山口の夢のみずうみ村にOTと見学に来られた。その日、夢のみずうみ村では、葉山靖明さん(片麻痺当事者であり、デイサービスけやき通り他を経営しておられる社長、我が友人)の仲間で、「片麻痺の会」を開催していた。葉山さん他の当事者の方々に、同じ片麻痺である優子さんは出会ってしまったのだ。それがターニングポイントである。初対面時、暗いなあ、おとなしいなあという印象であった。若くして脳卒中になられたのだ。想像しにくいという感じだが、我が夢のみずうみ村には石田陽子さんというスタッフがいる。高校2年生で発症し、私のリハビリ病院時代の患者さんであった。ご縁があって、夢のみずうみ村でマッサージ師の資格を取り働いていただいている。その彼女は陽気なのだ。だから初対面は暗いと感じていた。どっこい、今日の彼女は全く違っていた。「私の話は涙しますからバスタオルをご用意してください」と最初からジョークをかますのである。元気だ愉快だ明るい。何がそうさせたのか。「リスタートk~チャレンジ精神と新たな出会いが人生を変える」というテーマである。まさしく、夢のみずうみ村で、出会った体験が彼女の人生を変えた。活発に生きる視座をもたれ、チャレンジ。その場で衝撃なことが起こった。なんと、フィアンセが同席していたのだった。化粧をされたのにも驚いていたが、お嬢さんだからそれは当たり前程度に思っていたのに、どおりでおきれいになられたと思った。彼女の活発さは本来持っておられるものだと思うが、病気障がいは、それを阻んでいたと思う。それが、葉山さんや、夢のみずうみ村での出会いであったと確信できる。出口さんは右マヒで失語症であったのだが、まったくそれを感じさせない話しっぷりである。利き手交換、左手で書かれた言葉の学習のための所持訓練尾スライドは、ただただ驚いた。丁寧な文字。子ども2人を抱えての発症に、人生どう生きるかを苦悩された話に、同じ、右マヒ、父親である葉山さんとの障がいをどう受け止めこなすかの話。
3番手は伊藤恵理子さん。私も2度目、いや3度めの出会いである。タレントの平野レミさんみたいに元気な方と、奥田優子さんが紹介するような御仁。「この出会いに感謝!主婦の知恵袋!片麻痺で台所仕事~社会貢献へ」というテーマだ。片麻痺の料理の方法エトセトラの話が具体的内容であったが、とにかく、障がいをもって真っ暗であった中で出会った、作業療法士、そして、葉山さんたち当事者仲間。そうした出会いが、人生を変えたと、会場から異口同音に同じような話が出始めるきっかけの話題提供であった感がする。片麻痺料理の小道具を、同席していた中島萌OTが会場に高々と掲げて紹介。どこにもある品々をうまく活用する方法なのだ。知らなかったらできない皮むきも知っただけでできるようになる。当時者パワーのすごさである。
昼休み休憩をはさんで、ALSの森本和彦氏が登場。「障害受容を考える~人は障害を受容できるのか」というテーマ。気管切開され、車いすに寝たまま。伝の心を発表用にセットされ、奥様と仲間の方々(4人くらい)と昼休み中にセッティングされての開始。あらかじめ、パソコンで1文字ずつを「行と列」で選択して文章を作る作業をしてこられていたので、機械音で見事に朗読がスムースになされた彼の発表であった。理学療法士でご活躍であったことを司会者が伝える。よって、「障害受容」には学生時代より考えてこられたことや、学者や書籍での内容を紹介されながら、明確に、回想的な障がい受容などはありえないこと。(双方向であること)。障がい受容ということがあり得るのかと提起。全身寝たきりの森本さんの器械の声が会場に響く。重いテーマであるが司会役の葉山さんが話したことを受けて、会場で、森本さんが伝の心を打つ。そばで液晶画面を見る。「皆さんが受け止めてくれたことがうれしい」と。私がそこですぐ浮かんだのは、「これがいい」「このままでいい」と感じる心境であった。それを、森本さんの話を聴いて感じた。奥さんが作業療法士(OT)だと伺い、また感動。いい出会いをさせていただいた。夢のみずうみ学会では、舩後康彦氏以来、2度目のALSの方の登場であった。
5人目は山口宗彦氏。学校の生成だ他tころにバンドをつくられていて、そのメンバー共々の登場であった。「夢と出会いとやさしさと~音楽活動とともに」という発表。「視床痛」という脳卒中患者さんでも特異な痛みを持たれ、耐えられない痛みと、ギターを作業療法に取り入れ、ハーモニカで言語療法にも挑戦した話。実際に、メンバー6人による演奏。手話を交えての会場といった地となったコンサート。山口さんおハーモニカが響いた。みんなで手話しながら歌った「花は咲く」。とにかく素敵な発表であった。
最後に15分間で、発表者全員前に集合。私がマイクをにぎり、「第10回夢のみずうみ楽会」のおさらいをした。
①ヒトは誰もが自分の体の内側に「自分ダム」をもっている
②あたり一面に潜んでいる「感激の素(」味の素ではないですよとジョーク一発)を見つけ、感動感激すれば意思の水が湧く
③意思の湧水からどんどん水がたまり、自分ダムに一杯の水がたまるとそこが自分湖、夢のみずうみ、ですよ
④夢のみずうみに一杯水が、今日の会でたまったでしょ
⑤じゃあ、自分ダムの放水です。
⑥放水すれば水力発電です。あなたが自分で自分電力を生み出すのですよ。本日は、相当の自分電力を皆さんが発電されると思いますよ
⑦在宅で、障がいを持たれた方や病気で悩んでおられる方々が苦悩し、自分の内側のみに語り掛け、ますます孤立化し苦しまれれている方々に呼びかけましょう
⑧今日の皆さんの発表、姿、話の中味は、体験者ならではのすさまじい生きる力を与えてくださいました。当事者の方だからこそ生み出されるパワーです
⑨皆さん全てがおっしゃってます。出会いに感謝。障がいを持ったから生まれた出会い。
⑩葉山さんが言いました。障がい者の方は「障害を体験した方です」。私はそれを聴いて思いました。世の中に健常者はいない。居るのは「非当事者」だ。
素敵な 夢のみずうみ学会 奈良大会 ありがとうございました。
何か行動を起こさなければと全身が揺さぶられて 新幹線で東京に帰りながら、これを一気にまとめています
2017年、さっと新年が来て、あっという間に11月半分終わり、おっと、もう1月半分過ぎた。いつものように、動きが求められ、語り、動き、考え、悩み、時に笑いを交わし、うつむき歩き、走らなくてはいけないときは走り、「1年 365日」という時間は過ぎ去る。
ヒトとかかわり、人から力を頂き、人が生き、喜び、感動しあう中に居られる喜びを求め続ける人生でありたい。そうはいかない、現実が、目の前に様々、常に、横たわり、いかに対処するかを即座に対応しながら、また今年もあっという間に過ぎるのだろう。すこしでも 些細な出来事に最大の喜びを感じ取れる生きざまをしていこう。多くの方々に支えられての「夢のみずうみ活動」。
自分が、生きていることに感謝しながら、新年のメール更新を行いました。よろしくお願い申し上げます


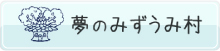 夢のみずうみ村
夢のみずうみ村